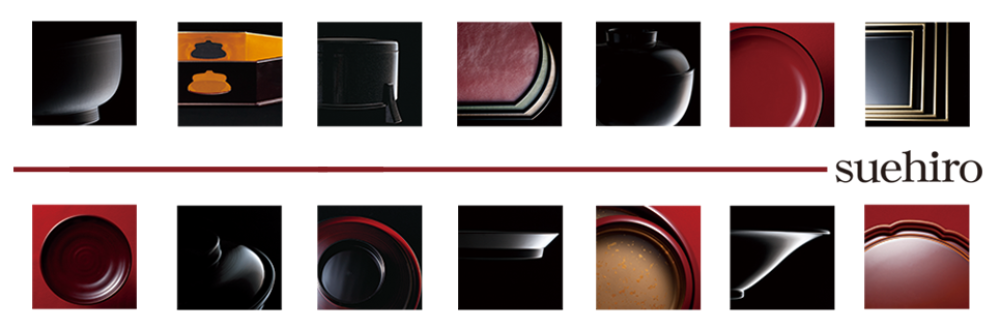皆様、こんにちは。株式会社末広漆器製作所の市橋です。
ここ越前では、紫陽花の花が雨に濡れて一層その彩りを増す季節となりました。梅雨入りを迎え、しっとりとした空気が流れる日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、本日は、漆器そのもののお話とは少し異なりますが、私たちが産地の将来を見据え、新たな挑戦として長年取り組んできた、新しいコーティング技術についてお話しさせていただきたいと思います。
木のお椀やお皿が持つ、自然な温もり。それは何物にも代えがたい魅力ですが、一方でこんなお悩みはありませんか?
- 塗装が剥げてきて、見た目が悪くなった…
- しばらく使わなかったら黒カビが…
- 口に入れるものだから、安全性は大丈夫?
私たちは、こうした目に見える悩みから見えない不安まで、様々な声を真摯に受け止めてまいりました。
「この素晴らしい木の器を、もっと気軽に、もっと長く、そして何よりも心から安心して使っていただくことはできないだろうか」。
そんな想いから始まった、私たちの10年にわたる挑戦の物語です。
- 木の器が抱える「塗装の剥げ」「黒カビ」の悩みを解決する新技術「GFC加工」
- “塗る”から”染み込ませる”への発想転換で生まれた、高い撥水性と防菌・防カビ効果
- 第三者機関が証明した、食品衛生法にも適合する確かな安全性
- 傷ついても修理して長く使える、サステナブルなものづくりへの想い
全ての始まりは、お客様の「困った」というお声でした
今から10年以上前のことです。
伝統的な漆器づくりに励む一方で、私たちは「木」という素材が持つ本来の魅力をもっと日常に届けたいという想いから、様々な木製品を手がけておりました。お椀やお皿、お弁当箱など、手に取ってくださったお客様からは「温かみがあっていいね」と嬉しいお言葉をいただく毎日。
しかし、同時にこんなご相談も受けるようになりました。
気に入って使っていたお椀の縁が、剥げてきてしまって…。
しばらく使わなかったら、内側に黒い点々(黒カビ)が…。見た目も悪いし、衛生的にも心配で。
心を込めて作ったものが、お客様の手元でその輝きを失っていく。そして、木の器を使うこと自体に、お客様が不安やためらいを感じてしまっている。ものづくりに携わる者として、これほど胸が痛むことはありません。
この「塗料膜の剥離の汚さ」や「黒カビの発生」という、木製品が宿命的に抱える問題を、なんとかして解決できないものか。それが、私たちの新しい挑戦の始まりでした。
「塗る」から「染み込ませる」へ。逆転の発想が生んだGFC加工
当初は、より強度の高い塗料を探したり、塗り方を工夫したりと、従来の方法の延長線上で試行錯誤を繰り返していました。しかし、なかなか根本的な解決には至りません。強度を上げれば木の風合いが失われ、見た目を重視すれば耐久性が犠牲になる…そんなジレンマに陥っていたある日、ふと、あるひらめきが舞い降りました。
「表面を『塗って』覆うのではなく、保護成分を素材自体に『染み込ませて』みてはどうだろうか」
まさに逆転の発想でした。外部からのコーティングで守るのではなく、素材そのものを内側から強くする。これが、私たちの独自技術「GFC加工」の原型となった「含浸加工」というアイデアです。
ガラス質の微粒子を含んだ液体を、木材の繊維の奥深くまで浸透させ、素材と一体化させる。これにより、木の持つ自然な風合いや呼吸を妨げることなく、内部から保護層を形成することができるのです。
この技術を確立したことで、私たちはさらに2つの重要な付加価値を実現しました。
GFC加工がもたらす2つの価値
- 高い撥水効果:水分が染み込みにくいため汚れもつきにくく、お手入れが簡単になります。
- 優れた防菌・防カビ効果:菌やカビの繁殖を抑制し、長期間衛生的に保ちます。
お客様が抱えていた悩みに、ようやく応えることができる技術が生まれた瞬間でした。
食卓に、確かな「安心」を。口に入れても安全なGFC加工
ここで、私たちがこのGFC加工を開発する上で、機能性と同じくらい、いえ、それ以上に重要視した「安全性」についてお話しさせてください。
GFCとは、Glass-Fiber Coating(グラスファイバーコーティング)の略です。その名の通り、主成分はガラス質の微粒子。皆様が毎日、直接口をつける器に使うものだからこそ、その安全性は絶対に譲れない一線でした。
私たちは、開発したGFC加工について、第三者機関による厳格な試験を依頼しました。その結果は、以下の通りです。
第三者機関による安全性試験結果
- 原材料に有害物質が含まれていないことを証明
- コーティングを施した製品から有害な物質が溶け出さないことを証明
- もちろん、食品衛生法にも適合しています
この客観的な証明は、私たちにとって大きな自信となりました。小さなお子様の離乳食用の器に、アレルギーなどを気にされる方の毎日のお皿に、ご高齢の方の使いやすいお椀に。どなたにも、心から「安心」してお使いいただける。
この安全性の確立こそ、GFC加工が完成したと言える、最後の、そして最も重要なピースだったのです。
「完璧ではない」からこそ、長く使える。私たちの考えるサステナビリティ
ここで一つ、私たちが大切にしていることをお伝えさせてください。
このGFC加工は、「絶対に傷つかない」「絶対に汚れない」という、いわゆる“完全完璧”な加工ではありません。もちろん、高い保護性能はありますが、例えば鋭利なもので強く擦れば傷はつきます。
しかし、私たちは、ここにこそ大きなメリットがあると考えています。
それは、「再加工が容易である」ということです。
もし、表面に非常に硬い膜を形成するような“完璧な”コーティングを施してしまうと、一度深い傷がついた場合、部分的な補修はほぼ不可能です。しかし、素材に染み込んでいるGFC加工は、表面を研磨し、再度加工を施すことで、新品に近い状態に蘇らせることができます。
気に入ったものを、もし傷つけてしまっても、修理してまた使い続ける。壊れたら捨てるのではなく、直して長く大切にする。この「再加工の容易さ」は、まさにSDGsが掲げる持続可能な社会の実現や、日本人が古来から大切にしてきた「もったいない」の精神にも通じるものだと、私たちは信じています。
木の器から、暮らしの様々なシーンへ。広がるGFC加工の可能性
このGFC加工の技術は、今では木製品の枠を越えて、様々な素材に応用されるようになりました。
- 陶器:吸水性のある陶器に施すことで、シミやカビを防ぎ、衛生的に。
- 紙・竹製品:水濡れに弱いという弱点を克服し、照明器具や耐久性の高い器などへ。
このように、一つの素材の悩みを解決するために生まれた技術が、他の素材の新たな魅力を引き出し、多岐にわたる分野でその可能性を広げているのです。このことは、私たちにとって大きな喜びであり、今後のものづくりの大きな原動力となっています。
まとめ:GFC加工で、木の器との暮らしをもっと豊かに
私たちの挑戦は、まだ始まったばかりです。これからも、このGFC加工の技術をさらに進化させ、新しい加工分野に挑戦していきます。
木の器との暮らしを、手入れの不安や安全への懸念から諦めていた方にこそ、この技術の可能性を知っていただき、再びその温もりを日々の食卓で感じていただけたなら、これほど嬉しいことはありません。
ご興味をお持ちいただけましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
株式会社末広漆器製作所
代表取締役 市橋